{
2008/11/07(金) }
私は中指をK子のオ○ンコに挿入したまま、
親指で敏感なクリ○リスを擦るように刺激を与えた。
私の右隣でソファーに座り肩を抱かれた状態のK子は、時々上半身を仰け反らせ、
喘ぎ声をあげ、とろけるような表情を見せていた。
やがてK子は、その小さな手で、スラックスの上から私の股間を弄り始めた。
そんな事をされなくても、すでに股間の愚息ははち切れんばかりに硬直していた。
K子は私に向き合うように体勢を変えると、私のシャツのボタンを外しながら、
首筋から乳首へと、その可愛らしい唇と舌先で刺激を与えはじめ、
私のボルテージは一気に高まってきた。
私が自らベルトのバックルを外すと、K子はシャツの次に私のズボンを脱がせ始めた。
腰を浮かせ、先端の引っ掛かりを踵から外すと、私は直ぐに全裸にされていた。
ソファーに座る私の股間に跪くように体勢を変えたTバック姿のK子の唇は、
上半身から段々と下がってきて、
そして硬直したチ○ポをその口に含もうとしていた。

私は、「まだシャワーを浴びてないから・・・」と言ったが、
K子はそんな事はお構いなしであった。
私の硬直したチ○ポをその小さな手で握り、舌を這わせ、口に含み、
そして顔を上下させた。
あまりの気持ちよさに、チ○ポから脳天まで電流が走り抜けたような気がした。
オシャブリするTバック姿のK子を上から見下ろし、私はK子の愛おしい小さな体を、
その手が届く限り触っていた。
しかしもう、ガマンが出来なかった。
私はK子の頬を両手で掴んで顔を上げさせ、上半身を起こし、
私の太股を跨ぐように導いた。
二人は何も言葉にしなくても、すでに同じものを同時に求めていた。
K子の腰を抱くように少し浮かせ、すでにトロトロになったオ○ンコの入り口に
硬直した男の先端部を当てた。
「あああぁ~~~」K子は喘ぎ声を上げながら、腰を深く沈めた。
私はK子の腰に両腕を回し、激しく腰を突き上げながら、K子の唇を求めていた。
親指で敏感なクリ○リスを擦るように刺激を与えた。
私の右隣でソファーに座り肩を抱かれた状態のK子は、時々上半身を仰け反らせ、
喘ぎ声をあげ、とろけるような表情を見せていた。
やがてK子は、その小さな手で、スラックスの上から私の股間を弄り始めた。
そんな事をされなくても、すでに股間の愚息ははち切れんばかりに硬直していた。
K子は私に向き合うように体勢を変えると、私のシャツのボタンを外しながら、
首筋から乳首へと、その可愛らしい唇と舌先で刺激を与えはじめ、
私のボルテージは一気に高まってきた。
私が自らベルトのバックルを外すと、K子はシャツの次に私のズボンを脱がせ始めた。
腰を浮かせ、先端の引っ掛かりを踵から外すと、私は直ぐに全裸にされていた。
ソファーに座る私の股間に跪くように体勢を変えたTバック姿のK子の唇は、
上半身から段々と下がってきて、
そして硬直したチ○ポをその口に含もうとしていた。

私は、「まだシャワーを浴びてないから・・・」と言ったが、
K子はそんな事はお構いなしであった。
私の硬直したチ○ポをその小さな手で握り、舌を這わせ、口に含み、
そして顔を上下させた。
あまりの気持ちよさに、チ○ポから脳天まで電流が走り抜けたような気がした。
オシャブリするTバック姿のK子を上から見下ろし、私はK子の愛おしい小さな体を、
その手が届く限り触っていた。
しかしもう、ガマンが出来なかった。
私はK子の頬を両手で掴んで顔を上げさせ、上半身を起こし、
私の太股を跨ぐように導いた。
二人は何も言葉にしなくても、すでに同じものを同時に求めていた。
K子の腰を抱くように少し浮かせ、すでにトロトロになったオ○ンコの入り口に
硬直した男の先端部を当てた。
「あああぁ~~~」K子は喘ぎ声を上げながら、腰を深く沈めた。
私はK子の腰に両腕を回し、激しく腰を突き上げながら、K子の唇を求めていた。
{
2008/11/05(水) }
K子を愛撫しながらシャツとブラジャーを脱がせた私は、ピッチリと太ももに張り付くような
Gパンを、なかなか上手く脱がせられないでいた。
そんな私がもどかしかったのか、K子は立ち上がり、自らGパンを脱ぎ捨てた。
ブラジャーとお揃いと思われる、黒地に花柄の飾りの付いたTバックをK子は履いていた。
K子の体は、とても40代の主婦とは思えないほどにキレイだった。
私は夢中になって乳房を揉み、乳首を口に含み、舌先で転がし、甘噛みした。
右手でK子の肩を抱き、左胸の乳首を舐めながら、左手でTバックの小さな布で辛うじて
隠されている陰部を、そっと触った。
すでにそこは、湿り気を帯びているようであった。
薄い布地の上から湿った敏感な部分を触ると、K子は「あぁ~ん」と、甘い声を出した。
クリ○リスと蜜壷の入り口を左手の中指で、縦にそっと擦るように触った。
私は乳首から唇を離し、K子に口づけをした。
K子は舌を絡め、顔をのけ反らせ、そして二人は何度も口づけを交わした。
パンティ越しにオ○ンコを触っている左手の中指には、
K子の柔らかな陰唇の感触が伝わってきていた。
K子のあえぎ声は、途切れ途切れに続いていた。

私は、左手の薬指でパンティを少しだけ横にずらし、中指で直にオ○ンコに触れてみた。
そこは既に、ヌルッとしたK子の淫液で溢れており、
私の中指は直ぐにでもイヤらしく濡れた蜜壷に吸い込まれそうであった。
中指でクリ○リスと蜜壷の入り口を交互に刺激しながら、私は相変わらずK子の
首筋から乳首を舐め続け、そして舌を絡めながらの口づけを繰り返していた。
そして、中指をK子のオ○ンコの入り口にそっと当て、少しずつ力を加えていった。
私の中指は、簡単にK子のオ○ンコに飲み込まれた。
その瞬間、K子はビクッと体をのけぞらせ、「ああぁ~っ・・」と声を上げた。

Gパンを、なかなか上手く脱がせられないでいた。
そんな私がもどかしかったのか、K子は立ち上がり、自らGパンを脱ぎ捨てた。
ブラジャーとお揃いと思われる、黒地に花柄の飾りの付いたTバックをK子は履いていた。
K子の体は、とても40代の主婦とは思えないほどにキレイだった。
私は夢中になって乳房を揉み、乳首を口に含み、舌先で転がし、甘噛みした。
右手でK子の肩を抱き、左胸の乳首を舐めながら、左手でTバックの小さな布で辛うじて
隠されている陰部を、そっと触った。
すでにそこは、湿り気を帯びているようであった。
薄い布地の上から湿った敏感な部分を触ると、K子は「あぁ~ん」と、甘い声を出した。
クリ○リスと蜜壷の入り口を左手の中指で、縦にそっと擦るように触った。
私は乳首から唇を離し、K子に口づけをした。
K子は舌を絡め、顔をのけ反らせ、そして二人は何度も口づけを交わした。
パンティ越しにオ○ンコを触っている左手の中指には、
K子の柔らかな陰唇の感触が伝わってきていた。
K子のあえぎ声は、途切れ途切れに続いていた。

私は、左手の薬指でパンティを少しだけ横にずらし、中指で直にオ○ンコに触れてみた。
そこは既に、ヌルッとしたK子の淫液で溢れており、
私の中指は直ぐにでもイヤらしく濡れた蜜壷に吸い込まれそうであった。
中指でクリ○リスと蜜壷の入り口を交互に刺激しながら、私は相変わらずK子の
首筋から乳首を舐め続け、そして舌を絡めながらの口づけを繰り返していた。
そして、中指をK子のオ○ンコの入り口にそっと当て、少しずつ力を加えていった。
私の中指は、簡単にK子のオ○ンコに飲み込まれた。
その瞬間、K子はビクッと体をのけぞらせ、「ああぁ~っ・・」と声を上げた。

{
2008/11/04(火) }
私は、セックスには心が必要だと、以前から感じていた。
だから、ただ性欲を満たすためだけのセックスには、あまり興味が無かった。
初対面の女性とセックスする場合でも、必ずお互いにある程度は心を開いてからでないと、
気持ちの良いセックスなど出来ないと思っている。
少なくとも、その数時間だけでも相手の事を愛おしいと感じられなければ、
やはりセックスなど出来ない。
だって、お互いに全てをさらけ出すんだから。
裸になって、普段は人に見せないところも見せて、舐め合って、感じ合って、
気持ちまで高めていくんだから。
だから、何気ない会話やセックスまでの時間を大事にしたいと
いつも思っている。

ホテルの部屋に入ると、しばらくの間K子と会話を楽しんだ。
その屈託のない笑顔に引かれた。
そしていつしか、K子をこの手で抱きしめたいと感じていた。
一度その柔らかな唇に口づけをしたら、その後はもう夢中だった。
K子の柔らかな乳房と腰に手を回し、感触を確かめ、シャツを捲り上げてブラジャーを外し、
その小さな乳首に唇を当てるのに、そう時間は掛からなかった。
ソファーに座った私の太股の上にK子を跨らせ、乳首への愛撫を続けるうちに、
彼女の腰が私の股間の前で前後に動き始めた事を私は見逃さなかった。
そして二人のエロスイッチがオンになった。
他人妻の、隠された本当の姿とは・・・?
↓ ↓ ↓
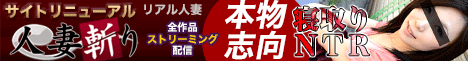
だから、ただ性欲を満たすためだけのセックスには、あまり興味が無かった。
初対面の女性とセックスする場合でも、必ずお互いにある程度は心を開いてからでないと、
気持ちの良いセックスなど出来ないと思っている。
少なくとも、その数時間だけでも相手の事を愛おしいと感じられなければ、
やはりセックスなど出来ない。
だって、お互いに全てをさらけ出すんだから。
裸になって、普段は人に見せないところも見せて、舐め合って、感じ合って、
気持ちまで高めていくんだから。
だから、何気ない会話やセックスまでの時間を大事にしたいと
いつも思っている。

ホテルの部屋に入ると、しばらくの間K子と会話を楽しんだ。
その屈託のない笑顔に引かれた。
そしていつしか、K子をこの手で抱きしめたいと感じていた。
一度その柔らかな唇に口づけをしたら、その後はもう夢中だった。
K子の柔らかな乳房と腰に手を回し、感触を確かめ、シャツを捲り上げてブラジャーを外し、
その小さな乳首に唇を当てるのに、そう時間は掛からなかった。
ソファーに座った私の太股の上にK子を跨らせ、乳首への愛撫を続けるうちに、
彼女の腰が私の股間の前で前後に動き始めた事を私は見逃さなかった。
そして二人のエロスイッチがオンになった。
他人妻の、隠された本当の姿とは・・・?
↓ ↓ ↓
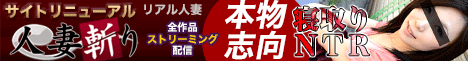
{
2008/11/02(日) }

K子の夢を見た翌日、私は彼女に2通のメールを書いた。
書きながら、夢で起こった出来事が次から次へと思い出されてきた。
両手で頬を挟んで間近で見たK子の優しい顔が、目を閉じると浮かんできた。
私に逢いに来てくれた事に感謝しながら、心を開いてくれた事に感謝しながら、
そして感じてくれている事に喜びを感じながら、愛おしさと切なさでゴチャ混ぜになった心で、
はち切れそうに硬くなったチ○ポをK子のトロトロに濡れたオ○ンコの奥深くまで挿入し、
大きな快感と共に腰を打ち付けていた事を思い出した。
そしてK子の顔を目に焼き付けようと必死だった事も思い出した。
彼女はもしかしたら天使だったのかもしれない・・・
ふとそんな気がしてきた。
空から舞い降りて来たかのように、突然私の前に姿を現したのだから、
そう思えても仕方の無い事だった。
私の前に突然姿を現したK子は、まさに理想の女性のような気がした。
小柄な体型、明るい性格、優しい笑顔、そしてセックスの時にみせるエロさやイヤらしさ・・・
まるで『昼は淑女、夜は娼婦』の言葉がピッタリのような気がした。
K子のセックスは、とても濃厚なものだった。
時には獣のように私を求め、時には私の感じている反応を楽しみ、
そして子猫のような姿で悶えた。
そしてなにより、その柔らかな笑顔が私を虜にした。

暖かくて柔らかで、優しくて愛おしくて、穏やかで可愛かった天使は、
しかしあっと言う間に私の前から消えてしまった。
私の心と体に大きな快感を与えるだけ与えて、彼女はいなくなった。
またいつの日にか、天使に逢えるのだろうか・・・
それとも、一夜限りの夢だったのだろうか・・・
そして、空からの贈り物が届いた。
天使から、メールの返信が来たのだ。
今の私には、それだけで十分だった。
{
2008/10/31(金) }
翌朝、私は久しぶりにゆっくりと目を覚ました。
おぼろげな頭の中で、夢とも現実ともつかない昨晩の出来事を思い出していた。
両手には、K子の温もりや感触が確かに残っている気がした。
優しい笑顔、切ないあえぎ声、柔らかな乳房、唇がチ○ポを包む感触、
唇を上下に動かした時のジュポジュポというイヤらしい音、
そしてなによりトロトロになったK子のオ○ンコの奥深くに挿入したチ○ポの心地よさ・・・
その全てが私の脳裏にはっきりと焼きついていた。
私は、夢の中で写真を撮った事を思い出した。
デジカメのメディアを確認すると、確かにK子の姿がそこにあった。
やはり夢ではなかったのか・・・。

私は、昨晩の全ての出来事を必死になって思い出そうとしていた。
楽しく心地よい時間をK子と共有出来たと思えたし、非常に気持ちの良い充実した
セックスができたと、自分自身でも感じていた。
しかし、彼女はいったいどうだったのだろうか?
そんな不安も私の気持ちの中には少なからずあった。
壊れるほどの充実感は味わえたのだろうか・・・
身も心もトロける程の快感を味わう事が出来たのだろうか・・・
楽しい一時を過ごせたのだろうか・・・
出会えた悦びを感じてくれたのだろうか・・・
後悔はしていないのだろうか・・・
そして、また逢いたい!と、思ってくれているのだろうか・・・

私は、少年のような恋心がK子に対して芽生えた事を、その切ない胸の内から感じ取っていた。
しかしその一方で、自分は分別のある大人であることも重々承知していた。
妻子ある身でありながら別の女性に恋心を寄せてはいけない、という法律や決まりなど、
どこにも無いハズだ。
それに、そんな事は結婚してから初めての事でもなく、2度目でも3度目でもなかった。
そんな都合の良い言い訳を、自分自身にしていた。
もう一度夢を見たい!
私は心からそう思っていた。
おぼろげな頭の中で、夢とも現実ともつかない昨晩の出来事を思い出していた。
両手には、K子の温もりや感触が確かに残っている気がした。
優しい笑顔、切ないあえぎ声、柔らかな乳房、唇がチ○ポを包む感触、
唇を上下に動かした時のジュポジュポというイヤらしい音、
そしてなによりトロトロになったK子のオ○ンコの奥深くに挿入したチ○ポの心地よさ・・・
その全てが私の脳裏にはっきりと焼きついていた。
私は、夢の中で写真を撮った事を思い出した。
デジカメのメディアを確認すると、確かにK子の姿がそこにあった。
やはり夢ではなかったのか・・・。

私は、昨晩の全ての出来事を必死になって思い出そうとしていた。
楽しく心地よい時間をK子と共有出来たと思えたし、非常に気持ちの良い充実した
セックスができたと、自分自身でも感じていた。
しかし、彼女はいったいどうだったのだろうか?
そんな不安も私の気持ちの中には少なからずあった。
壊れるほどの充実感は味わえたのだろうか・・・
身も心もトロける程の快感を味わう事が出来たのだろうか・・・
楽しい一時を過ごせたのだろうか・・・
出会えた悦びを感じてくれたのだろうか・・・
後悔はしていないのだろうか・・・
そして、また逢いたい!と、思ってくれているのだろうか・・・

私は、少年のような恋心がK子に対して芽生えた事を、その切ない胸の内から感じ取っていた。
しかしその一方で、自分は分別のある大人であることも重々承知していた。
妻子ある身でありながら別の女性に恋心を寄せてはいけない、という法律や決まりなど、
どこにも無いハズだ。
それに、そんな事は結婚してから初めての事でもなく、2度目でも3度目でもなかった。
そんな都合の良い言い訳を、自分自身にしていた。
もう一度夢を見たい!
私は心からそう思っていた。




























